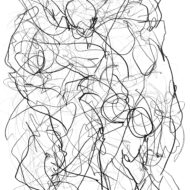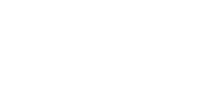私は画家ですが、絵を販売しているわけではありません。
時々、海外の方から「その絵が欲しい」と言われ、お送りするぐらいです。
じゃ、本当の画家じゃないですね、と、ややディスられるトーンで言われると
「はい、職業画家ではありません」と申し上げます。
「画家」を職業名詞だと思っておられる方とお話しするときはいつもこれです。
私が今まで出会った職業名詞としての画家の判断基準は以下の通りです。
1 東京芸大出身でなければダメ
2 美術教師は画家になれなかった人
3 画壇に所属してないとダメ
4 もしくは村上隆みたいな感じでないとダメ
5 デッサンは写真みたいにリアルに描ける
6 絶対に絶対に生身のモデルさんで描く人でないとダメ
これら、実は究極的には「お金持ちじゃないとダメ」っていうことなんです。
本当に。
この1〜6が結局お金の問題だ、と悟ったので、大学卒業と同時に絵を辞めました。
意地悪く言い換えると「お金持ちじゃない人間は絵を描いてはいけない」という「システム」になっているんです。
いや、そんなことないですよ、と思われる方は、どうぞそのまま行ってください。私は無理でした。
もういいっす。あたしお金ないんで。さよなら。
という感じで、卒業してから20年間、本当に一度も絵筆をとりませんでした。
貿易商社に勤めるようになり、そこで「商品」とは何かということがよくわかるようになりました。
商品は一定の需要と供給があり、どちらかがなくなれば市場淘汰され、消えていきます。
その商品が消えることで、それを生産している会社も市場から淘汰されます。
そうやって健全な経済活動が自然と維持されていくのが、一応の資本主義社会の原則です。
この観点から「絵」という「物」と「事」と「システム」を商材として冷徹に見るようになりました。
正確性には欠けるかもしれませんが、あくまでも私の認識は以下の通りです。
まず、「物」としての絵画。需要と供給が全く成り立ってません笑。
0円でも売れなくて、1億円よりももっと高くても売れるもの、なーんだ?です。
ということは適正価格も存在しません。市場淘汰も働きません。
絵画は特殊な商品だとは思っていましたが、最近はそもそも「商品」足りえていないのでは、と思っています。
それをベースに、まず、1枚2枚売れたからって、生計が成り立つわけありませんよね。
国民年金とかどうするんでしょうか。法人じゃないから、1号被保険者?本当に大変です。
生活防衛資金を、少なくとも半年分は貯蓄しておかないとダメです。
「絵」という「商品」が顧客に与えるベネフィットは何でしょうか。
- 宗教画のように「それを見ると心が安らぐ」と言うメンタルヘルス
- 「モノホンの小磯良平作品」といったブランドステータス
ぐらいが顧客に与えるベネフィットです。二つとも必要がないので、私は絵を買えませんし、買いません。
なかなかピンポイントにこのセグメントに入る潜在顧客を見つけるのは至難の技です。
このレッドオーシャンを勝ち抜いて、自分の作品を売る営業力が必要です。
一般企業の営業職として必死で働いているサムライジャパンよりも、もっともっと顧客を虜にする力が要ります。
百貨店などでサロン化するのは「顧客を探さなくてもあちらから来てもらえる仕掛け」として良い手法だと思います。
そして、晴れて超有名な画家になったとします。
すごい豪邸に華麗なアトリエを持ち、倉庫には1作数千万円の評価額の作品が保管されているとします。大抵130号とかの絵です。とてもおめでたいことなのですが、人生の終盤で最後の一山が来ます。
これ、遺産相続の際に、絵が高ければ高いほどガッツリ相続税が取られます。原則現金納付です。
ということは、あなたが存命中のうちに何としてでも作品を売り「尽くさない」と、遺された家族がえらい目にあいます。
サクサク売れるような物でもないし。こういう状態で銀行って貸付できるんでしょうか。
もう、東京芸大出身でないとダメとか、画壇がどうとか、そういうのがどうでもよくなる生々しい現実が、資本主義社会で生きている以上は地響きを轟かせて襲ってきます。
ということで、結論。
売れないときは売れない時に、売れたら売れたで、どっちにしろかなりのキャッシュがないとやっていけないのが「職業」画家です。しかも、どの段階でもキャッシュが必要です。
いや、もう私が生きていける世界じゃないですね。
では、私が画家じゃないのか、と言えば、いいえ、私、画家ですよ笑。(続く)